犬の金〇袋という、かわいそうな花( ;∀;)~オオイヌノフグリ~

早春というより、冬の終わりと言ってもいいくらいに早い季節に道端で目にする青い小花。
この花の名前をご存知でしょうか(。´・ω・)?

こちら、「オオイヌノフグリ」という オオバコ科クワガタソウ属の越年草(2年草)学名: Veronica persica 。
越年草とは秋に芽吹いて、冬を越し、早春に開花・結実するとその一生を終え枯れてしまう仲間ということです。
種の表記では「2年草」や「秋まき一年草」なんて呼び方をされる場合も多い。
実際のところ花が咲くまでその存在に気付くことは少ないですね(;^ω^)
だいたいは「雑草」でひとまとめにされてしまう。
でも早春の鮮やかな青はよく目を引きます。
群生することも多くよくよく見ると花もかわいいです(*´▽`*)
目次(*´▽`*)
花の姿とそぐわない、ひどい名前「キンタマ」って( ノД`)シクシク…
名前を漢字で書くと「大犬陰嚢」
そうです、大きな犬の金〇袋って意味です(/ω\)
あの可愛い花のどこが金玉なんだ?って思うでしょ(。´・ω・)?
それはコレ、オオイヌノフグリの花後、実が付いた姿なんですが……

よく見ると(@_@)

(''Д'')あ……
そういわれたら、もうそれにしか見えない(;^ω^)
これ、あの花の後にできる果実。
あんなに目立つ花に目を向けずよくもこんな地味な部分を名前に採用したなと感心します。
”大犬”がいるってことは、”小犬”もいるんです
実はこのオオイヌノフグリ、こんなにどこでも見かけるけど、もともと日本にあった花ではないんです(゚Д゚)ノ
もとは明治の初期に入ってきたヨーロッパ原産の草花。
それがあっという間に日本中に広がったらしい。
西洋タンポポもそうだが、外来種は日本の同種を駆逐してその範囲を広げていく。
日本にはもともと「イヌノフグリ」という野草が存在していた。
これはよく見かけるオオイヌノフグリより花が小さく色も薄い。
分布は広いが今では絶滅危惧種に指定されるほどに数を減らしている。
残念ながらうちの近所でお目にかかることはできなかったので詳しい比較はこちらの方のブログを参考に、
比べると結構違うけど単体で見たら見分けできるかな(;^ω^)
あっという間に姿を消す青い花「オオイヌノフグリ」
オオイヌノフグリの花の寿命は1~2日、それでも結実率は95%とかなり高い。
その理由は自分で動いて受粉するから!
(; ・`д・´)え?自分で動く?
そう思うかもしれませんが、もちろんテクテク隣の花まで歩いていくわけではありません。
1日たって花が終わりかけると、他との授粉をあきらめて雄しべが「ぐぐ~」っと自分の雌しべに近づいて『自家受粉』(自分の花粉で種を作る)を行うんです。
この特徴的な2本の雄しべがクワガタソウ属の特徴。
昆虫のクワガタの顎にみたててるんですね(*'▽')

この機能により、自家受粉で確実に結実することで、多くの種をつけることができるんです。
ある研究では1個体あたり平均545個の種子が生産されたという調査結果もある!
どおりでたくさん目にするわけですね(^_^;)
オオイヌノフグリには、もっといい別名もあるんです!
「犬の陰嚢(イヌノフグリ)」なんて名前じゃなくて、もっときれいな呼び名もあるんです。
例えば「瑠璃唐草」「天人唐草」「星の瞳」など、
でも、瑠璃唐草はネモフィラも同じ名で呼ばれるから、まあ、そっちの方がふさわしいかな(;^ω^)
天人唐草も山岸涼子の漫画で紹介されているけど、なぜその名で呼ばれるのかは見つけられなかった。
読んだことないけどそんな描写あるのかな?
数ある中で一押しなのが「星の瞳」誰がつけたか知らないけど、ぴったりじゃないですか?
真っ青な花の中心が白く輝く、まさに夜空に輝く星の様です(●´ω`●)
ぜひ今後はオオイヌノフグリ改め「星の瞳」と呼んであげてくださいネ(*´▽`*)
まとめ

今回は早春の青い小花、オオイヌノ…ちがった「星の瞳」についてご紹介しました(≧▽≦)
学名だとベロニカ・ペルシカ。
英名では Bird's-eye、Cat's-eyeなどという名がつけられています。
ペルシアと名前がついているけど、原生地がペルシャかどうかはよくわからないらしい。
あまりにも繁殖力が強く、どこでも我が物顔で広がっているから、もうどこが原産なのかわからないんですね(^_^;)
小さくて見過ごされがちですが、春の訪れを告げる草花は他にもいっぱいあるんですよ。
お花屋さんに行くだけが園楽じゃないんです!
たまには足を止めて、足元で頑張る草花を眺めてみてはいかがでしょうか?
では、皆様よい園楽を~(。・ω・)ノ゙
今回の参考書籍


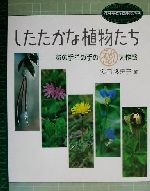


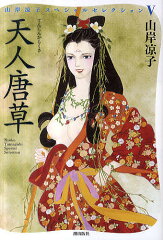



“犬の金〇袋という、かわいそうな花( ;∀;)~オオイヌノフグリ~” に対して1件のコメントがあります。